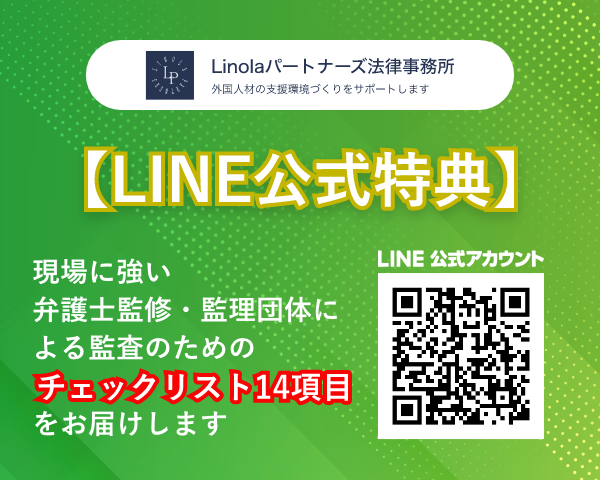特定技能外国人の住宅支援に関する法的要件と受け入れ企業の責任
- #特定技能
\この記事を読むとわかること/
| ✔︎ 特定技能外国人の住宅支援に関する受け入れ企業側の法的義務がわかる ✔︎ 住宅支援の社宅や寮の提供方法と受け入れ企業の利益禁止規定についてわかる ✔︎ 特定技能外国人向けの住居支援に関する法令違反のペナルティについてわかる |
受け入れ企業には、特定技能外国人の受け入れに際し適切な住居を確保する責任があります。
さまざまな基準がある中で、受け入れ企業として具体的にどのように住居を手配すればよいか、どのような法的リスクに備えればよいか悩む方も少なくないのではないでしょうか。
今回は、受け入れ企業が行うべき住居支援や各種法令で定められている基準、利益禁止規定をはじめとする法令違反時のペナルティと是正対応に至るまで詳しく解説します。
弊所でもお問い合わせの多い事例ですので、ぜひご参考になさってください。
1 特定技能外国人の住居支援の法的義務と背景

| 特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等) 第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項を記載しな ければならない。 一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容 ハ 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人とな ることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。 |
出典:法務省 1号特定技能外国人支援に関する運用要領「特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)」
特定技能外国人を雇用する受け入れ企業は、特定技能外国人の安定した生活を確保するために住居支援を行う法的義務を負っています。
これは、特定技能外国人が安心して働ける環境を提供することが、関係法令の定める適切な受け入れ体制の一環とされているためです。
外国人材の受け入れに伴い、受け入れ企業は居住環境の提供、賃貸借契約の支援、保証人となるなど、住宅に関する包括的なサポートを行わなければなりません。
また、適切な住宅環境を提供することは、優秀な外国人材の定着率向上が期待できますので、受け入れ企業にとって重要な要素となることは明らかです。
2 住宅提供に関する主な規定(住宅基準、契約のルール)

| 居室の広さは、一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し、1人当たり 7.5 ㎡以上を満たすことが求められます(ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保 している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く。)。 |
出典:法務省 1号特定技能外国人支援に関する運用要領13頁「(3-1)適切な住居の確保に係る支援 〔義務的支援〕」
特定技能外国人の居住環境は、最低7.5㎡以上のスペースが必要とされ、これは法務省が定める基準です。
さらに、受け入れ企業が賃貸借契約を結ぶ場合には、外国人労働者の同意を得る必要があり、彼らの権利を守るために契約内容の透明性と理解を得るための配慮は企業側にとって不可欠な要素となります。
また、家賃の支払いにおいても受け入れ企業が利益を得ることは禁止されており、合理的な家賃の設定が義務付けられている点にも注意が必要です(後述)。
これらの規定は、特定技能外国人が安心して生活できる基盤を提供するための重要なルールのひとつといえるでしょう。
3 受け入れ企業と特定技能外国人の賃貸借契約における法的責任

受け入れ企業が特定技能外国人と賃貸借契約を締結するケースでは、居住環境の整備と契約内容の明示・説明の機会がとても重要です。外国人の権利保護の観点から、契約内容の理解をサポートするための翻訳や通訳が必要となることがあります。
また、賃貸借契約において受け入れ企業が保証人になるケースでは、家賃滞納などのリスクに対して企業側が法的責任を負うこともあり、日頃から万が一に備えたサポート体制を構築しておかなければなりません。
契約内容や保証の責任を明確にしておくことは、外国人労働者の権利を守ることはもちろんですが、受け入れ企業にとっても健全な運営を行うために不可欠です。
4 特定技能外国人の住宅確保・3つのケース

| ① 特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結する ② 特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結する ③ 特定技能所属機関が所有する社宅等を1号特定技能外国人の合意のうえ住居として提供する |
具体的な支援方法や注意点について注意すべきポイントをおさえておきましょう。
【CASE1】特定技能外国人が自ら住居を探す場合の支援方法
特定技能外国人が自分で住居を探す場合に受け入れ企業が行うべき支援は以下のとおりです。
(1) 不動産仲介業者の紹介と契約時のサポート
特定技能外国人が自ら住居を探す場合、受け入れ企業は信頼できる不動産仲介業者を紹介することが一般的です。
また、契約時には必要な手続きの説明や翻訳サポートを行います。
先述のとおり、この段階の丁寧かつ適切な対応がとても大切ですので、契約内容の理解を サポートし外国人労働者がトラブルなく住居を確保できるようにしなければなりません。
(2) 連帯保証人の問題と受け入れ企業の役割
| ① 1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも・ 特定技能所属機関等が連帯保証人となる ・ 利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、特定技能所属機関等が緊急連絡先となるのいずれかの支援を行う |
出典:法務省 1号特定技能外国人支援に関する運用要領13頁「(3-1)適切な住居の確保に係る支援 〔義務的支援〕」
外国人労働者が賃貸借契約を結ぶ際には、連帯保証人の確保が困難なケースが多いため、受け入れ企業が保証人になるか、保証会社を利用することが一般的です。
また、家賃債務保証業者を利用した場合は、企業側が保証料を負担する必要があります。
もし、受け入れ企業が保証人となる場合は、家賃滞納時のリスク管理を含めた施策を備えておくことも必要となるでしょう。事前に弁護士のリーガルチェックを受けるなどして、抜け漏れのチェックを行うことをおすすめします。
【CASE2】受け入れ企業が賃貸借契約を結ぶ場合の支援方法と条件(敷金・礼金の負担)
このケースは、外国人労働者の初期費用の負担を軽減でき、スムーズに住居を確保することができるでしょう。
(1) 敷金・礼金の負担について
受け入れ企業が特定技能外国人のために賃貸借契約を結ぶ際には、敷金や礼金を負担することが実務上一般的です。
また、受け入れ企業が自ら賃借人となるときの注意点としては、1号特定技能外国人に社宅として貸与する際は経済的利益を得てはなりませんので注意が必要です。
(2) 家賃滞納時の受け入れ企業の対応策
家賃滞納が発生した場合、受け入れ企業には速やかな対応が求められます。
まず、受け入れ企業が連帯保証人になっている場合、滞納分を一時的に肩代わりすることも考えられますが、滞納を未然に防ぐための施策やサポートもまた重要です。
【家賃滞納を防ぐための施策例】
| ・住宅管理会社や保証会社と連携して、万が一に備える・外国人労働者が支払いに困らないようにするためのサポート体制の構築 (→具体的には、可処分所得を増やす工夫など)・困っていることがないかなど、労働意欲が低下するような起きていないか、日頃からコミュニケーションを蜜に取っておく など |
【CASE3】 受け入れ企業が社宅や寮を提供する場合の支援方法と注意点
受け入れ企業がおさえておくべき「利益禁止規定」の防止策や罰則、また、罰則時に受け入れ企業が行うべき適切な対応についてみていきましょう。
(1) 家賃設定に関する利益禁止規定
※②及び③の場合とは「受け入れ企業が賃貸借契約を結ぶ場合」「受け入れ企業が社宅や寮を提供する場合」のことです。
| ②及び③の場合であって特定技能所属機関等が自ら賃借人となるときは、1号特定技能外国人に社宅等を貸与することにより経済的利益を得てはなりません。1号特定技能外国人から費用を徴収する場合については、借上物件の場合、自己所有物件の場合に応じて、次のとおりでなければなりません。 ・ 借上物件の場合 借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数 料・更新手数料・途中解約金等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額 ・自己所有物件の場合 実際に建設・改築等に要した費用(土地の購入代・土地の造成費用等土地に関 する費用は除く。)、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額 |
出典:法務省 1号特定技能外国人支援に関する運用要領14〜15頁「(3-1)適切な住居の確保に係る支援 〔義務的支援〕」
受け入れ企業が提供する社宅や寮では、合理的な家賃設定が求められ、受け入れ企業が利益を得ることは禁止されています。直接的な負担はもちろんのこと間接的な負担をさせることもできませんので注意が必要です。
家賃については、受け入れ企業が賃貸物件に支払う実費を基準に設定され、外国人労働者にとって負担の少ない水準でなければなりません。
これらは、労働者が不当な負担を強いられることを防止するために定められています。
(2) 社宅や寮の提供時における不当利益の防止策
前述のとおり、家賃は実際の支出に基づいた合理的な金額で設定しなければなりません。
また、契約内容を明確にし、労働者が納得のいく条件で住居を利用できるようにすることが大切です。
契約前の説明時点から、つまり初動の時点がとても大切です。
この時点で、いかにコミュニケーションを取り契約内容について理解を得ておけるかが、後のトラブルを回避するために重要となることはご理解いただけるのではないでしょうか。
(3) 利益禁止違反時の罰則と対応
受け入れ企業が利益取得禁止規定に違反した場合、出入国在留管理庁(以下、入管)からの監査や罰則の対象となる可能性があります。
罰則を避けるためには、受け入れ企業において提供住居の家賃設定を合理的な水準に保たなくてはならないことは先述のとおりです。
もし、違反が発覚した場合は、是正措置を講じ適切な家賃設定に戻したうえ、再発防止のための是正措置・対応の報告を入管に対して行わなくてはなりません。
【利益禁止規定違反時の受け入れ企業が行うべき対応】
| ・速やかに現場対応の経験豊富な弁護士に相談して適切な対応をすることが大事! ➡︎ 初動を謝ると取り返しのつかないことになりかねません。 |
5 住居探しにおける言語サポートの重要性

外国人労働者が住居を探す際には、言語の壁が大きな障害となるため、契約内容や住居条件の理解を助けるための通訳や翻訳などの「言語サポート」が不可欠です。
受け入れ企業が言語サポートを提供することで、労働者の安心感が高まり、住居に関するトラブルを未然に防ぐことが期待できます。
【外国人労働者に多い住居トラブルの例】
| ・宗教上の慣習 ・夜中に騒ぐ ・地位域ごとのゴミの捨て方の指導(収集日、分別方法、粗大ゴミの捨て方など) ・近隣住民とのトラブル ・空き地など無断の立ち入り ・喫煙ルール など |
6 特定技能外国人向けの住居基準違反時のペナルティと是正対応

特定技能外国人向けの住居基準と違反時のペナルティについて確認していきましょう。
(1) 居住スペースの最低基準(7.5㎡以上の必要性)
特定技能外国人が住む住居の居住スペースは、最低7.5㎡です。
(2) ルームシェア時の広さの計算方法と注意点
| なお、ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が7.5㎡以上でなければなりません。 |
出典:法務省 1号特定技能外国人支援に関する運用要領13頁「(3-1)適切な住居の確保に係る支援 〔義務的支援〕」
複数人でルームシェアする場合、1人当たりの最低面積を満たしているかが必要です。
各部屋の広さや居住者数に応じて、適正な住居基準を満たすよう配慮しなければなりません。
(3) 住居基準違反時のペナルティと是正措置・対応
| ○ 特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機 関に委託した場合でも、当該登録支援機関の体制からして実効性ある支援を行うことができないと認められるときは、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準(特定技能基準省令第4条第1号の規定)により受入れが認められない場合があります。 |
出典:法務省 1号特定技能外国人支援に関する運用要領4頁「(3-1)適切な住居の確保に係る支援 〔義務的支援〕」
住居基準を満たさない場合、入管からの指導や改善命令を受けることがあり、違反が続くと罰則が科せられる可能性があります。
【罰則】
| ・今後、受け入れができなくなるおそれ |
違反が発覚した際は、速やかに是正措置を講じ、基準を満たす住居環境を確保しなければなりません。
この時に行う是正対応は非常に重要ですので、この分野に精通した実務経験豊富な弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
また、必要に応じて関係各所に報告する義務があります。
7 住居提供後の受け入れ企業の義務とは?

特定技能外国人への住居提供が無事に完了した後、受け入れ企業が行うべき対応についてみていきましょう。
(1) 住居に関する報告義務と自治体への届け出
特定技能外国人の住居に関する届出やその他関係手続きを行う際は、関係行政機関の窓口へ同行し、 書類作成などの必要なサポートを行うことが企業側に義務付けられています。
具体的には、外国人が90日以上日本に滞在する場合、住居情報を自治体に届け出なければなりません。
また、住居が変更された場合も迅速に届け出を行い、居住状況を最新のものに保ちます。
もし、報告義務を怠った場合は、行政指導や監督、是正命令、受入れ停止等の処分が科されることがありますので注意が必要です。
(2) 住居に関する定期的な面談と状況確認
受け入れ企業は外国人労働者の生活環境を把握するために、住居に関する定期的な面談を行いましょう。
慣れない日本での生活環境において、労働者が日常生活に不満や問題を抱えていないかを確認し、必要に応じて適切なサポートを行いましょう。
(3) 住居変更や転職時の支援内容
外国人労働者が転職や契約解除となる場合、受け入れ企業は新たな住居を見つけるためのサポートを行うことが一般的です。
特定技能外国人が日本での生活を継続できるようにするために、転職支援に伴う住居確保や移転手続きに関するサポートを行わなければなりません。
8【参考】技能実習生からの移行に伴う特例(居住基準の緩和)

技能実習生から特定技能へ移行する際、一部の住居基準が緩和されるケースがあります。
技能実習生用の住居基準である4.5㎡の規定は、移行直後の一定期間適用されることがあり、これは受け入れ企業が迅速に人材を受け入れられるよう配慮されているものです。
ただし、長期的には特定技能外国人の基準である7.5㎡以上の住居が必要です。
9 サマリー

特定技能外国人を雇用する受け入れ企業には、安定した住環境を提供し、労働者が安心して生活できるよう法的義務が課されています。
特に、契約面での抜け漏れや間接的な負担金を誤魔化している企業は注意してください。今すぐ立て直しを図りましょう。
また、義務的な支援はもちろんのこと任意的な支援に工夫を凝らすことで、双方にとってベストな関係を築いている企業はやはりトラブルが少ないです。
受け入れ企業側の住宅支援サポートや任意的支援が適正であれば、労働意欲も増し企業にとっても大きなメリットとなります。
実務上では、慣習の違いやコミュニケーション不足などが要因となり、些細な住宅トラブルから想像を超えるようなトラブルに発展することも珍しくありません。
万が一の事態に備えて日頃から外国人労務に精通した法律の専門家のサポートを受けることができる体制を整えることをおすすめします。
この記事を書いた「Linolaパートナーズとは」

あなたのお悩み相談できます
オンラインでの相談も可能です記事を読んで疑問に思っている点を確認したい
自分たちの問題点の洗い出しをしたい
ご要望がございましたら、お電話・お問い合わせフォームからお気軽にお問合せ下さい。